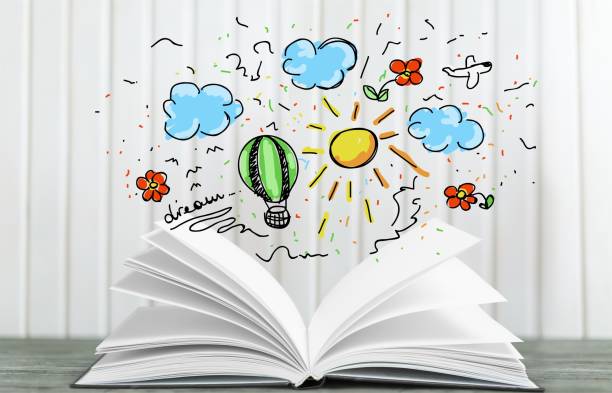「うちの子、自分のことを話したがらないんです」
「何を考えているのか、親にも分からなくて…」
そんな悩みを抱えるお家の方は多いのではないでしょうか。
実は、こうした“自分の気持ちを言葉にできない”という現象の背景には、
「ナラティブ(=自分の物語)」をうまく紡げていないことが関係しています。
ナラティブ・アプローチとは?
ナラティブ・アプローチとは、心理学や教育学の分野で注目されている「物語的自己理解」の考え方です。
人は誰でも、自分の経験を“ストーリー”として語ることで、
「自分は何者なのか」「どんな意味があったのか」を理解しようとします。
たとえば、
「テストで失敗した」だけでは“事実”にすぎません。
でも、「あの失敗があったから、次は計画を立てるようになった」と語れるようになると、その出来事は“成長の物語”に変わります。
つまりナラティブ・アプローチとは、
子どもが自分の体験に意味を見出す力を育てる心理的サポートのことなのです。
「自分を語れない子」に見られるサイン
最近では、小学生の段階から「自己理解が浅い」「自分を表現できない」子が増えています。
学校現場でも、自己紹介や作文になると手が止まってしまう子どもが少なくありません。
この背景には、
〇 失敗を避ける文化(間違えたくない)
〇 大人からの評価基準に合わせる習慣
〇 忙しすぎて内省する時間がない
といった現代的な要因が重なっています。
つまり、自分の内側を見つめる“心の余白”が不足しているのです。
この状態が続くと、自己肯定感が低下し、挑戦への意欲も薄れていきます。
ナラティブが育む3つの力
ナラティブ教育が注目される理由は、
子どもの“心の根っこ”を育てる3つの力にあります。
① 自己理解力
自分の経験を言葉にすることで、「自分の考え」「気持ち」「得意・苦手」を整理できます。
これはキャリア教育や人間関係にも直結する大切な土台です。
② 意味づけ力
出来事をポジティブに再解釈できるようになります。
「失敗=ダメなこと」ではなく、「次へのヒント」として捉えることで、
レジリエンス(回復力)も高まります。
③ 自己肯定感
「自分の物語を語れる=自分を受け入れている」状態。
他人と比較するのではなく、自分の成長を感じられるようになります。
家庭でできる!ナラティブの育て方3ステップ
ステップ①:「そのとき、どう感じた?」を聞く
出来事を“結果”ではなく“感情”から振り返る質問が効果的です。
たとえば、
「テストどうだった?」よりも
「やってみて、どんな気持ちだった?」と聞くと、
子どもが自分の感情を整理しやすくなります。
ステップ②:「過去→現在→未来」をつなぐ声かけ
「前はこうだったけど、今はここまでできるね」
「次はどうしたい?」
といった“時間軸”を意識した対話が、
子どもの中で“成長の物語”を作り出します。
ステップ③:「書く・描く」で言語化をサポート
口で話すのが苦手な子には、
「今日のハッピー3つ書こう」などの簡単な日記形式もおすすめ。
視覚的に整理することで、
自分の経験を「ストーリー」として見られるようになります。
子どものできる形で感情を外に出す練習を意識すると、ナラティブ力が育ちます。
「語る力」が子どもの未来を変える
ナラティブ力が育った子どもは、
他人の意見に流されず、自分の価値観で判断できるようになります。
・人間関係で悩んでも「私はこう感じた」と整理できる
・失敗しても「次につながる意味」を見つけられる
・将来の夢を、自分の言葉で語れる
つまり、ナラティブとは単なる「話す力」ではなく、
人生を“自分の物語として生きる力”。
親が「聞く姿勢」をもって、子どもの言葉を受け止めるところが出発点となります。
まとめ
ナラティブ・アプローチは、
「できごとを意味ある物語に変える」心理教育です。
子どもが自分の体験を語り、
そこに“自分なりの意味”を見出す力は、
自己肯定感・レジリエンス・人間関係力のすべてを支える基盤になります。
親ができるのは、“教えること”より“聴くこと”。
「話してくれてありがとう」と言葉を返すだけで、
子どもの中に「自分を語る安心感」が芽生えていきます。
関連記事はこちら⇩